想定外の事態に対処するには
今年はよく台風が発生し日本列島に上陸していますね。
想定外の物事に対処するには、日頃からどうすればいいのでしょうか?
そんな事を考えていたら沖縄県に特別警報が発令されました。
大変、参考になるサイトを見つけました。
連載 プロマネの現場から第56回 「想定外」 を考える 蒼海憲治(大手SI企業・金融系プロジェクトマネージャ)より
早速、引用してみます。
昨年の東日本大震災直後、圧倒的な被害を前に、東京電力や政府など原発関係者から異口同音に「想定外」という言葉が連発されました。その際のニュアンスが、「想定外だから仕方がない」という自己を免責するトーンだったことに違和感を持たれた方は多いのではないでしょうか。
システム構築プロジェクトにおいても、本番カットオーバー以降に発生した障害に対して、上流から流れてきたデータやユーザが行ったオペレーションやシステム環境の相違を指して、「想定外」の事象が発生した、という言い方をよく耳にします。
しかしながら、昨年の震災以来、安易に「想定外」と言うことをたしなめられるようになりました。それは、「想定外」ではなく、考慮不足、知見不足、スキル不足、チェック不足、判断ミス等々ではないのですか、と問われるようになりました。
想定外を便利な言葉として扱い、自らの考え不足を隠していたと思います。反省です。
想定外についてまた引用をしてみます。
今回は、この「想定外」について、少し考えてみたいと思います。
震災直後に「想定外」という言葉が繰り返されたことに対して、2週間後の3月中旬に、社団法人土木学会、地盤工学会、日本都市計画学会の3学会の声明が公表されました。阪田憲次・土木学会会長が会見で、「安全に対して想定外はない」。そして、「われわれが想定外という言葉を使うとき、専門家としての言い訳や弁解であってはならない」と指摘されたことが強く印象に残っています。
畑村洋太郎さんが委員長をつとめた「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」の中間報告書の最後にある「考察と提言」において、「想定外」を想定できなかったことが、真の原因であり、今後の教訓とすべきことが指摘されています。また、畑村さん自身の著作、『「想定外」を想定せよ!―失敗学からの提言』(*1)においても、「想定する」とは何か、また、「想定外」とは何かが、説明されています。
人がものを考えるにあたって、考える範囲を決める必要があります。この考える境界を決めることを「想定する」といいます。人は、考える範囲を決めないと、きちんと考えることができません。
すなわち、「想定」とは、考えるために必要不可欠なものです。しかし、「想定」が、物事を考えるために人為的に、意図的に作られた「境界」に過ぎない以上、「ありうることは起こりうる」。
≪どんなに発生頻度が低く、「想定外」のことであっても、
起こる可能性が論理的に0パーセントでない限り、起こるときには起こる≫
だから、どのように「想定」を置いて考えたか。また、その結果、「想定」の外には何があるかを合わせて考えなければ、「想定」した人の思惑を超えて、「想定外」の事象は、常に起こり続けます。
中略して、想定の設定についての理由について引用してみます。
失敗学の権威の畑村洋太郎氏の話は、本当に考えさせてくれます。
そして、問題がある「想定」を設定してしまうのには、いくつかの理由があります。
1.思い込み
複数の人が同じモノを見ても、同じ事実認識ができるとは限りません。人には無意識・無自覚なうちに、さまざまなバイアス、フィルターがかかっているからです。それは、先入観や既成概念、過去の経験、立場・職位などによって、モノの捉え方が異なるからです。このバイアス、フィルターに対する意識・自覚をした上で、三現主義(現場、現物、現実)からスタートできるかが大切になります。
2.希望的な観測
最初は、「そうあって欲しい」と思っていたことが、いつのまにか「そうなっているはずだ」に変化してしまう。
3.思考停止
思うことがはばかられる。恐れ多い。見たくない。考えたくない。
問題が起こった時の影響範囲や被害の大きさが想定できた場合でも、その対策に要するコストが莫大な時、そのような問題はめったに起こらないと考えることで、回避策や軽減策等の対策も取らなくなります。これに、希望的な観測が加われば、なおさらこの傾向に拍車がかかります。
もしリスク軽減策をとろうとすると、いったん問題が起こらないと整理したことに対して、なぜ対策が必要になるのか、また、本来の回避策のためには莫大なコストを必要とするなら、そもそもの費用対効果がなりたたないのではないか、という指摘に答えられないからでは、と思います。
4.「人は忘れる」
「人は忘れる」という大原則があります。そして、人間の忘れっぽさには、「3」の法則がある、と、畑村洋太郎さんは、『未曾有と想定外』(*4)で指摘されています。
3日 (個人)飽きる
3月 (個人)冷める
3年 (個人)忘れる
30年(組織)途絶える・崩れる
60年(地域)地域が忘れる
300年(社会)社会から消える
1200年(文化)起こったことを知らない
過去に経験した大きな事故やトラブルも、当事者がいなくなり、その話を伝える人もいなくなると、徐々に記憶が減衰し、なかったものとされてしまう。そして、忘れ去られたことは、想定から外れてしまいます。
5.想像力の不足
この点については、前述した柳田邦夫さんの著作(*2)の中で、大きく2つの観点の想像力の必要性を指摘されています。
≪問題は、専門家の想像力にあると、私は言いたい。
想像力とは何か。第一には、起こり得る事故の形態を予測する能力である。
設計や運用の「前提条件」が満たされなかった場合や、「前提条件」としての想定ラインを超えた問題が生じた場合に、どのような事故が発生するかを想像する必要がある。
そのように脳の回転を可能にするには、「前提条件」を絶対視しないで、
現実の多様さやダイナミックスに対して、謙虚であることが求められる。・・≫
≪第二は、予想外の形で事故が発生した場合に、周辺の住民や地域にどのような事態が生じるか、その被害の規模と実相についてリアルに想像する感性と思考力が求められるということである。≫
参考サイトでの参考文献
(*1)畑村洋太郎『「想定外」を想定せよ!―失敗学からの提言』NHK出版
(*2)柳田邦男 『「想定外」の罠―大震災と原発』文藝春秋
(*3)竹内啓『偶然とは何か――その積極的意味』(岩波新書)
(*4)畑村洋太郎『未曾有と想定外─東日本大震災に学ぶ』(講談社現代新書)
(*5)デビッド・アレン『ストレスフリーの仕事術―仕事と人生をコントロールする52の法則』(二見書房)






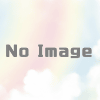

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません